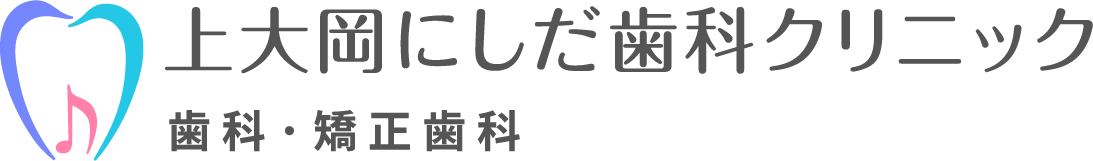Features
Features
① 一般歯科、歯科矯正の2つの柱を基礎として
密に連携をとって治療を行っている。
一般歯科の定期検診、幼稚園、小学校の学校検診で「歯並びに異常」があると、、、
「矯正科の先生に診てもらいましょう」
矯正歯科で矯正を始める際に、、、
「虫歯があるから、他の歯医者で治してきてくださいね。それから矯正を始めましょう」
と、どちらの場合も別の歯医者に行く事となり、治療を進めていく事がよくあります。
なぜでしょうか?
一般歯科を主体としていると、矯正歯科は専門性が高く、しっかりとした技能を習得するのに時間もかかるため、矯正治療まで手が回らない事が多いのが現状です。またその逆も同じで、矯正の診療を主体としていると、一般診療になかなか手がまわらない事が多いのです。
当院では一般治療を主体とする私と、矯正治療を主体とする妻が2人とも常勤で治療を行っていますので、一般の検診、矯正診療の検診、どちらの場合においても異常を早期に発見する事ができます。早期発見が一般診療においても、矯正診療に置いても大切であり、また、(時間的にも、金銭的にも)患者様にとって負担の軽減になります。

② 精密治療への取り組み
当院では歯科医師、衛生士ともに拡大視野による精密な処置を心がけております。
歯科衛生士はsurgitel製の6倍ルーペ
歯科医師はsurgitel製の8倍のルーペを使用
また、Leica製マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を4台導入しており、歯科衛生士、歯科医師が見ている映像を患者様と一緒に確認し、説明、診療を行っております。
「視えなければ診れない」
一般的には保険の診療は歯科医師、歯科衛生士ともに、肉眼で行われることが多いですが、当院では基本的な保険の診療でもライト付きの6倍以上の拡大視野にて治療を行っています。

歯科衛生士、歯科医師どうしで拡大した視野を共有することはもちろん、患者様とも一緒に確認をしていただいております。
全員で共有ができないと、しっかりとした治療、患者様への説明ができないのは明らかです。
肉眼において、“見たところ大丈夫そう=虫歯、歯石がない“わけではありません。
あっても視えていないだけです。視えなければ診れないのです。
肉眼での、
「はい、これでお掃除終わりです。」「綺麗に治りましたね」
本当ですか?見えてますか?
ちなみに、ルーペ、マイクロスコープの全国の普及率はどれくらいでしょう?どちらもともに10%程度です。
お口の中は暗く、狭く、唾液が多い環境です。
なぜこのような厳しい環境だとわかっているのに、普及しないのでしょうか?それは高額な設備投資、取得難易度の高さ、保険診療とのアンマッチなどがあげられます。
| 裸眼 (多くの歯科院) | ルーペ | マイクロ スコープ | |
| 見える範囲 | 肉眼(1倍)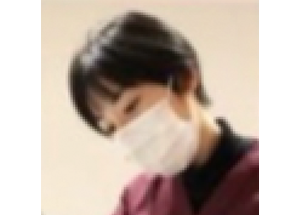 | 衛生士6倍 歯科医師8倍  | 4~20倍 |
| 見え方の違い | 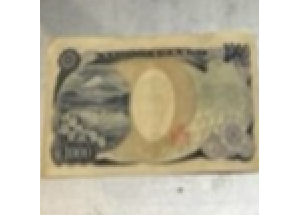  | 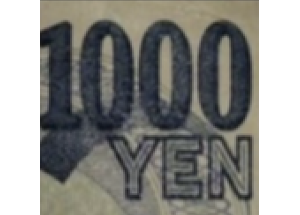  | 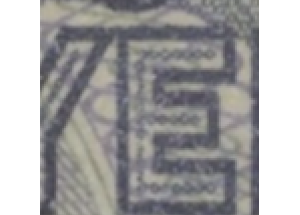  |
| 世界での普及率 | 100% | ヨーロッパでは多く (正確なデータはなし) | アメリカの根管治療専門医では ほぼ100% |
| 日本での普及率 | 100% | 10% | 10% |
| 日本で普及が進まない原因 | |||
| 導入費用 | 0 | ★★★ (数万〜数十万) | ★★★★★ (数百万~1,000万) |
| 技術の 取得難易度 | ★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 保険のシステム | 基本的な保険治療 | 使用の有無に限らず 保険点数が変わらない | 保険診療の枠組みの中では 時間が確保しにくい (海外では基本 すべての治療が自費) |
| 当院での保有数 | - | 7台 | 4台 |
| 当院での 使用対象 | 矯正治療 (全体の把握が大切なため) | 保険、自費、 全ての治療 | 自費(一部保険対象) |
当院では歯科衛生士になる前の学生のうちからスタッフ同士で6倍でのルーペのトレーニングを始めます。
衛生士になってからはマイクロスコープを習得し、日本顕微鏡学会の顕微鏡(マイクロスコープ)認定衛生士の資格を所有しているものもおります。これらの取り組みにより、当院では「少しでも質の高い医療を患者様に提供したい」という思いで、ルーペ、マイクロスコープを使用しております。
私たちと同じ目線でお口の中を確認していただき、いつまでもご自身の歯で美味しくご飯が食べられるよう一緒に頑張りましょう。
③ 患者様の「不安」に配慮した治療
「歯医者が嫌い」
私もです!
麻酔されるのも治療されるのも嫌です。
しかしこの「歯医者が嫌い」なぜ嫌なのか?これは患者様によって様々です。
においがダメ、音が嫌だ、何をされているか分からないのが嫌い、先生が怖そう、痛いのが嫌い。
中でも多いのは痛み、麻酔に関する事です。しかしこの「痛み」、実はこれも患者様によって感じ方は様々です。
チクッはいいけど、押される感じが嫌だ
麻酔の液が苦いのが嫌だ
麻酔したときの心臓のドキドキが嫌だ
治療中に痛いのが嫌だ
多少の痛みは我慢するけどとにかく注射を見るのも嫌だ
頬を引っ張られるのが嫌だ
麻酔をされた後の感覚が嫌だ
上記のように多岐にわたります。
当院では患者様の不安や苦手を少しでも解消できるようにまずはしっかりお話をさせていただき、その上で患者様ひとりひとりに合った方法を選択させていただきます。
痛みに関して
針を入れる時のチクッとする痛みに関しては表面麻酔(塗る麻酔)を使わせていただき、その後通常の麻酔を行います。
特に前歯の方は感覚が敏感なため、入念に行います。
麻酔を入れるときの押される感覚は、下顎、上顎の舌側で強く感じます。歯茎が厚く引き締まっていたり、骨が硬いためです。 これに関しては薬液を温め、機械で制御された電動の麻酔を使い、ゆっくり薬液を入れる事によって緩和されます。
麻酔のドキドキについて
そもそも一般的に使う麻酔液にはエピネフリン(血管を収縮させて麻酔の効く時間を長くする薬)が入っています。
この薬液が心臓まで達すると、心臓に対してはドキドキと鼓動が早くなります。
そのため、健康状態に問題がなければこの時のドキドキはエピネフリンと、緊張からくるものなので、特に問題はありません。
ただし、健康状態に問題がなくてもこのエピネフリンに対して過敏な方もいらっしゃいますので、場合によってはエピネフリンの入っていない麻酔薬に変えさせていただきます。
その他にも、患者様が不安を抱えたままにしていただきたくないので、しっかりと説明の時間をとらせていただきますし、どうしても音が嫌であればイヤフォンで音楽を聴いていただいてもかまいません。(ただし治療の内容によってはこまめにコミュニケーションをとる必要がございますので、ご相談ください) 全ての要望に答えられる訳ではないかと思いますが、患者様の不安を少しでも解消し、快適に治療を受けていただければと思っておりますので、お気軽にご相談ください。
④ 徹底的な衛生管理
当院では、当たり前の事ですが、衛生管理を徹底しております。
患者様ごとに手袋を変える事はもちろん、患者様が使用される、コップ、エプロンについても患者様ごとに使い切りの物を使用しております。
また、定期的なメンテナンスの際にブラッシング指導に使用した歯ブラシは患者様に差し上げております。
器具の滅菌についてはクラスB滅菌器(世界最高水準)のオートクレーブを使用し、タービン(歯を削る器具)についても、専用のオートクレーブを使用しております。
また、キッズスペースでお子様が遊ばれたおもちゃについても、消毒を行っております。

⑤ 各世代の患者様に配慮した院内設備
当院ではなるべくご家族で来院していただくことにより、今後の予防に役立てたいと思っております。
ご家族で来ていただけると、骨格的にも似てきますし、お食事の内容、タイミング、歯磨き粉など、生活面でも似たような傾向になり、今後のお子様などの予防にもつながるからです。
そのため院内の設備も各世代の患者様に配慮しております。
・キッズスペース
・広い診療スペース
・ベビーカー、車いすでもそのまま入っていただけます
・院内バリアフリー
・照明
昼間はご年配、お子様連れでも入りやすく明るく、夜は仕事帰りの方にゆっくりしていただけるように、照明を暖色になるよう工夫をしております

予約システム
深夜など受付時間外からでもインターネットでご予約をしていただけます
問診票
専用のタブレット端末により、一問一問答えを選択していただくので、直感的に答えていただけます。
ご年配の方でも一問一問なので文字も大きく、選ぶだけなので簡単に操作できるかと思います。
わからなければ、もちろんお手伝いさせていただきますのでお気軽にお声がけください。

⑥ 音楽歯科
私は音楽と、歯科は密接に関わりがあると考えています。
高校時代吹奏楽で管楽器をやっていた経験、歯科医としての立場から、音楽をされている方々に生涯にわたって音楽を楽しんでいただけたるためにはどうしたらいいかという事を考えております。音楽は生涯に渡り趣味としてつづけていけるものだと思います。
日本人の10人に1人は吹奏楽経験者と言われており、日本は世界一の吹奏楽大国だそうです。また吹奏楽以外のピアノ、管弦楽なども含めると相当な数になるかと思われます。楽器の演奏は、バイオリンは顎で支え、管楽器はマウスピースを口で咥える。声楽も、細かい事を言えば肺から出された空気が、声帯を振動させ、口腔内で響き音色となります。
では突然顎が痛くなったり、歯がなくなるような事があれば、思うように演奏できるでしょうか?音楽の経験、知識を持つ人間として音楽をされている方々に伝えていければと思っております。